皆さんこんにちは。
人工呼吸器の構造についていまさらながら説明していきます。
人工呼吸器に関しては過去にも多く記事を書いていますのでご参照ください。
人工呼吸器の歴史
私たちが息を吸うとき、横隔膜が下がって、胸腔内が陰圧になることで吸気が起こります。
その陰圧をもとに1929年に鉄の肺といわれる人工呼吸器が作られました。鉄の箱に頭以外を入れて、陰圧をかけることで胸壁を膨らまし、吸気を作っていたようです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E3%81%AE%E8%82%BA
それより前にも同様に陰圧式の呼吸器はあったようですが、ヨーロッパのポリオ大流行によりこの鉄の肺が普及したそうです。
それでも救えない命が多くあり、現在と同様の陽圧式の人工呼吸器が開発されたようです。
そこから改良が続けられ、現在に至るまでかなりの歴史があるわけです。
現在の人工呼吸器の構造
さて前置きが長くなりましたが、構造を見てみましょう。
なお今回は人工呼吸器が送り出す空気をガスと表現しています。
弁
人工呼吸器にも弁があるのです。弁はバルブともいいますね。弁といえば心臓の弁を思い浮かぶ方が多いかと思いますが。。
人工呼吸器には “吸気弁” と “呼気弁”があります。
それぞれ簡略に説明すると
吸気弁は、呼吸器回路の始点に。呼気弁は吸気回路の終末にあります。
基本的にはこのふたつの弁はどちらかが開いていて、どちらかが閉まっているという関係にあります。
吸気の際
吸気の時は、人工呼吸器からガスを送り出しますね。
その時、吸気弁は開いていて、呼気弁は閉じています。
吸気弁は呼吸器回路の始点にありましたね。送る際は開いています。
呼気弁は回路の終末にありましたね。ここが閉まることによって肺にガスがたまるのです。
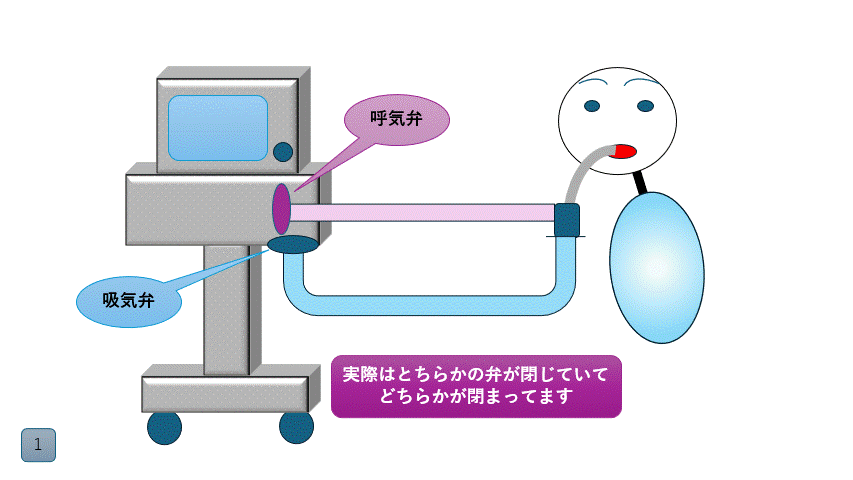
呼気の際
呼気の際、人工呼吸器ができることはひとつしかありません。
吸気弁を閉じて、呼気弁を開けることです。
肺にガスがたまっている状態で、ガスを送るのをやめて回路始点の吸気弁を閉じる。そして回路終末の呼気弁を開く。
すると肺にたまったガスは肺の弾性(縮もうとする力)により収縮し、呼気弁からガスが流れ出ていくということです。
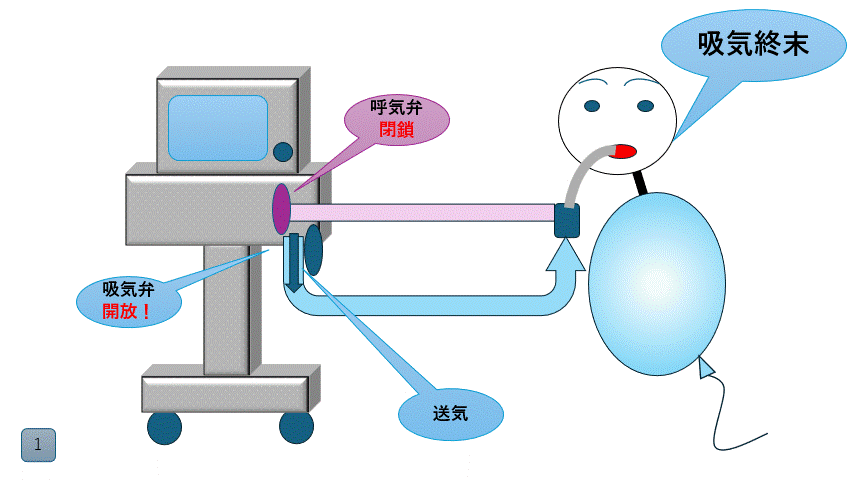
人工呼吸器はこの二つの弁を使って吸気と呼気を作っていた訳ですね。
換気によるガスの流れ
基本的には人工呼吸器は、空気配管と酸素配管に接続します。(空気配管が不要なものもある)
それぞれの配管から空気(酸素21%)と酸素(100%)を設定の酸素濃度(FiO2)になるような割合で取り込こみます。
それを設定した圧や量を、吸気弁を開けて肺に送ります。この際に呼気弁(回路の終末)は閉じているので弾性のある肺が膨らみます。
設定した圧や量を設定した時間送り終わったら、吸気弁が閉じると当時に呼気弁が開きます。
すると肺が縮み、呼気弁にガスが流れていく訳です。
余談ですが、人工呼吸器は呼気弁から排出されたガスはフィルターを通りますが、人工呼吸器から排出されます。
ここが手術室で使う麻酔器との違いです。麻酔器は呼気を再度CO2を吸着させて大部分を再循環させます。麻酔器は吸入麻酔を使うからですが、それはまたいつかお話しますね。
まとめ
本日は人工呼吸器の歴史から簡単な構造について説明しました。
少し退屈でしたでしょうか。笑
でも弁に関しては意外と重要ですので覚えておいてくださいね。
何か、お気づきの点がございましたらコメント欄にご記入ください。
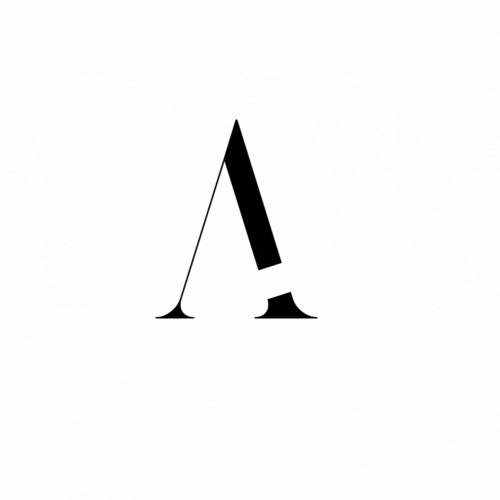




コメント